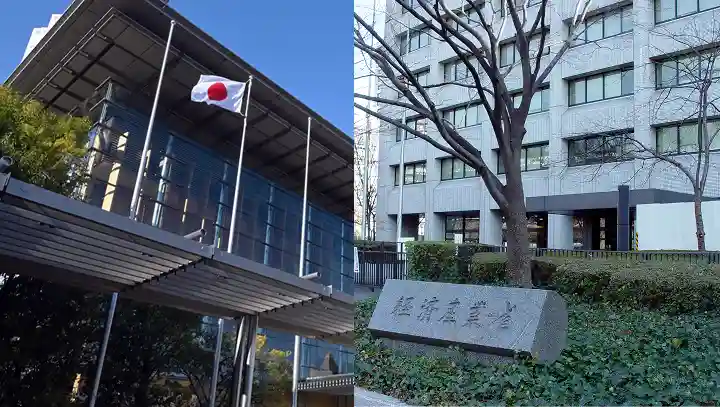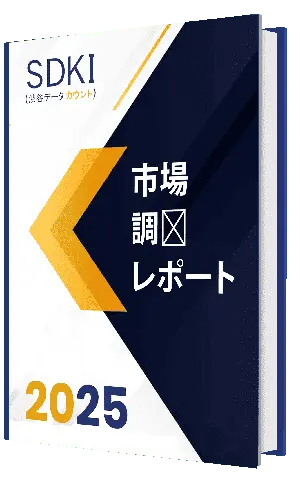日本初の純国産量子コンピュータ:世界の技術競争力の転換点
SDKI Analytics によって発行されました : Nov 2025
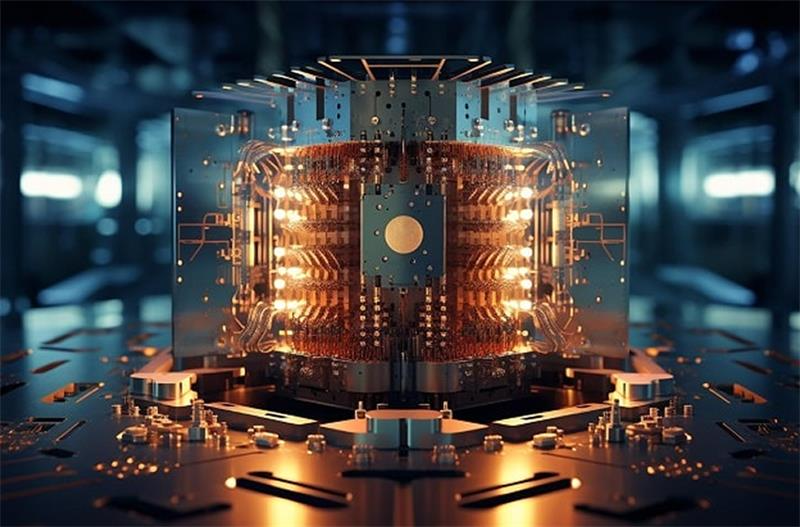
最近、日本で大きな技術開発が達成されました。2025年7月、文部科学省(MEXT)と科学技術振興機構(JST)の支援を受けた大阪大学の研究者らは、ハードウェア、ソフトウェア、材料すべて日本製で構築された国内初の量子コンピュータを発表しました。従来のシステムでは極低温部品や制御部品の輸入に依存していましたが、このプラットフォームは完全に国産です。この発表は科学における画期的な出来事であり、21世紀で最も戦略的に争われている技術の一つである量子コンピュータにおいて、日本の自立性を確保する意志を示すものです。
日本の量子の旅を追う
日本は長年、精密製造、ロボット工学、自動車エレクトロニクスの分野で世界をリードしてきましたが、量子コンピューティング技術のフルスタック化には遅れをとっています。これを是正するため、政府は2024年3月に量子HPC(高性能コンピューティング)の野心を強調した白書を発表し、米国などと共同で100,000量子ビットのシステム構築を目標としています。これに先立ち、2023年10月にはRIKENと Fujitsu株式会社が64量子ビットの超伝導マシンを開発しました。 クラウド アクセス経由で利用できますが、インポートされたコンポーネントがまだ組み込まれています。
量子ハードウェアのサプライチェーンが地政学的な争点となっている今、国内製造のマイルストーンは重要な意味を持つ。例えば、米国、ヨーロッパ、中国は量子コンピューティングにおける主導権を争っている。日本の取り組みは、量子コンピューティングにおける主導権争いへの直接的な対応であり、日本貿易振興機構(JETRO)の報告書は、(ジェトロ)2025年10月、国産量子コンピュータを日本の量子産業化推進の基盤として位置づけます。
特に、自動車・モビリティ分野において、量子コンピューティングは、ルート物流、サプライチェーンのレジリエンスといった高度に非線形な最適化問題の解決、次世代バッテリー化学のモデリング、軽量構造のための材料開発の加速といった分野で大きな可能性を秘めています。さらに、日本が量子技術の自給自足を目指していることは、企業にとって、海外のプロバイダーに依存するのではなく、より自国に近い場所でこれらの技術を活用できる機会を提供し、産業統制と戦略的柔軟性の双方を強化することが期待されます。
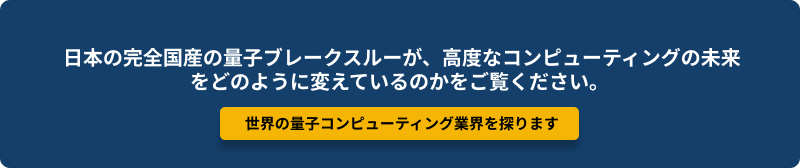
日本の国産量子コンピュータを理解します
このシステムは超伝導量子ビットを用いています。超伝導量子ビットは、ミリケルビン温度(約10 mK)まで冷却された微小回路で、電気抵抗を除去して量子挙動を解き放ちます。この日本製システムの特徴は、希釈冷凍機及びパルスチューブ冷凍機(極低温)、チップパッケージング、低雑音増幅器、ケーブル配線、ソフトウェアスタック(OQTOPUS)など、すべての主要サブシステムが国産化されているという点です。例えば、
- 希釈冷凍機はULVAC CRYOGENICS INCから供給されており、超低温インフラは日本製であることが確認されています。
- オープンソースでローカルに開発されたソフトウェア スタックにより、ユーザーは、オペレーターとユーザー向けのオープン クォンタム ツールチェーン (OQTOPUS) を介してクラウド プロトコルを通じて量子システムにリモートでアクセスできるようになります。
- このシステムには、2025年大阪・関西万博での展示が接続されており、来場者は量子マシンにリモートアクセスして簡単なプログラムを実行することができた。
運用面では、日本の企業や研究者は、海外からの輸入への依存度を低減しながら量子実験に取り組むことができるようになります。また、動的交通モデリング、バッテリー最適化、物流シミュレーションなど、日本の基準や規制枠組みに近いモビリティ特有のユースケースに合わせて、ハードウェア/システムアーキテクチャをカスタマイズすることも可能になります。
量子自立の実現に向けて日本が直面する課題とは?
こうした進歩にもかかわらず、重大な技術的及び商業的課題が浮上しています。量子コンピューティングにおける自立を目指す日本の取り組みを阻む課題について、以下に分析します。
- 高いエラー率:超伝導量子コンピュータは、高いエラー率と量子ビット数の少なさという問題を抱えています。日本のシステムは国産ですが、当初は28量子ビットのシステムで、ロードマップでは2025年10月までに約100量子ビットの実現を目指しています。
- コストとスケーラビリティの問題:極低温冷却、量子ビット制御エレクトロニクス、そして誤り訂正のオーバーヘッドは、いずれも依然として高価で電力消費量が多い。したがって、日本が実証実験から産業グレードの量子インフラへと拡張できるかどうかは、大きな試金石となるだろう。
- 量子エコシステムの開発:モビリティに特化したアプリケーション向けの量子エコシステムは未だ未開発です。自動車OEMとティア1サプライヤーは、この課題を克服するために、量子マシンから価値を引き出すための独自のアルゴリズムとワークフローを開発する必要があります。
- 国際競争の激化:中国、米国、ヨーロッパなど世界の主要国は量子ハードウェアとソフトウェアを並行して進歩させており、日本の優位性が損なわれる可能性がある。
最後に、ガバナンスと産業政策の観点からは、データ主権、輸出規制、量子技術の二重使用の性質に関する疑問が残ります。
SDKI分析アナリストの視点:モビリティと自動車業界のステークホルダーへの影響と成長機会
アナリストによる提言は、日本の量子エコシステムに関する実践的かつデータに基づいた評価を提供します。これらの洞察は、ステークホルダーが核心的な課題に取り組み、量子コンピューティングがもたらす機会を活かすために必要な先見性をもたらすことを可能にします。
自動車OEM、ティア1サプライヤー、モビリティサービスプロバイダーの多くは日本に拠点を置いており、また日本企業と緊密に連携しているため、この節目は戦略的な転換点を示唆しています。実行可能な提言としては、量子技術への対応を研究開発ロードマップに組み込むことが挙げられます。企業は量子技術の能力評価を段階的に進めていく必要があります。これは、大阪大学のような国内の量子プラットフォームとの連携を意味します。
第二に、関係者は日本のサプライチェーンにおけるポジショニングを活用できます。バッテリーシステム、パワーエレクトロニクス、極低温サブシステム、量子センサーなど、自動車エコシステムを構成する部品サプライヤーにとって、国産量子ハードウェアの実証は、新たな輸出や共同設計の機会を生み出す可能性があります。さらに、量子グレードのハードウェア要素は、先進モビリティシステムにおいても需要が見込まれる可能性があります。
第三に、ユースケースの共同開発と協働です。量子応用はまだ初期段階にあるため、モビリティ企業は日本の研究コンソーシアム(QIQB、RIKEN, Fujitsu)と提携し、実証事例を共同で創出する必要があります。例えば、危機後のEVサプライチェーンにおける量子技術を活用した最適化、次世代軽量合金のシミュレーション、スマートシティ展開のための量子技術を活用した交通流モデルの活用などが挙げられます。
第四に、マクロ傾向との関連性はステークホルダーにとって不可欠です。この動向は、技術主権、脱炭素化、サプライチェーンのレジリエンスといったより広範なテーマと結びついています。日本のモビリティ企業にとって、国内で量子技術の能力を構築することは、バリューチェーンにおける自社の地位を強化し、海外の量子ハードウェアへの依存を軽減するのに役立ちます。また、これは半導体のより広範な傾向や、自動車分野におけるハードウェアのみから量子技術を活用したソフトウェア定義システムへの移行とも整合しています。
したがって、モビリティの意思決定者は、完全な商用量子優位性が実現するまで待ってはなりません。そうしないと、基礎となるエコシステムの構築を逃す可能性があります。
日本の量子コンピューティングエコシステムで次に何が起こるのか?
この 10 年間で注目すべき 3 つの重要なマイルストーンは次のとおりです。
- 日本のマシンを初期量子ビットからスケールアップすると、約 100 量子ビットの目標とそれ以降の目標に近づくことになります。
- 日本におけるモビリティ及び電池材料分野における信頼できるパイロットユースケースの出現。
- 共同開発やサプライヤーパートナーシップモデルを通じて、自動車OEMやサプライヤーを中心としたグローバル企業が日本の量子エコシステムにさらに参加します。。
日本がハードウェアの規模と関連するアプリケーションフレームワークの両方を実現できれば、量子ハードウェアとモビリティソフトウェアのハブとしての地位を再構築できる可能性があります。世界のモビリティ業界にとって、これは国家レベルの技術革新が戦略レベルに昇華する瞬間です。問題は「量子が重要になるかどうか」ではなく、「量子を推進するインフラをいつ、誰が構築するのか」です。したがって、日本の完全国産量子コンピュータは、今後の注目すべき始まりを示すものです。




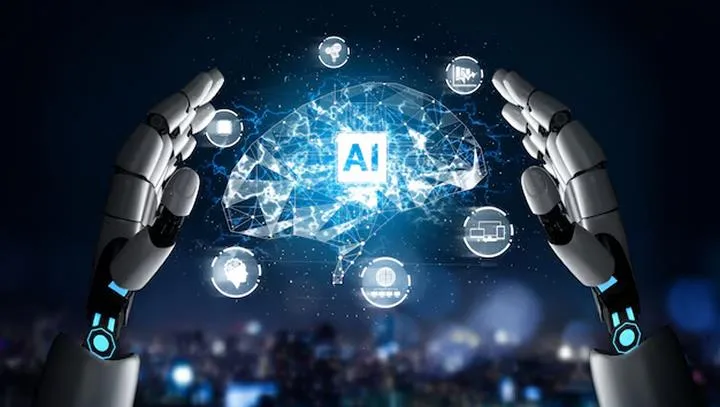
_1765973632.webp)