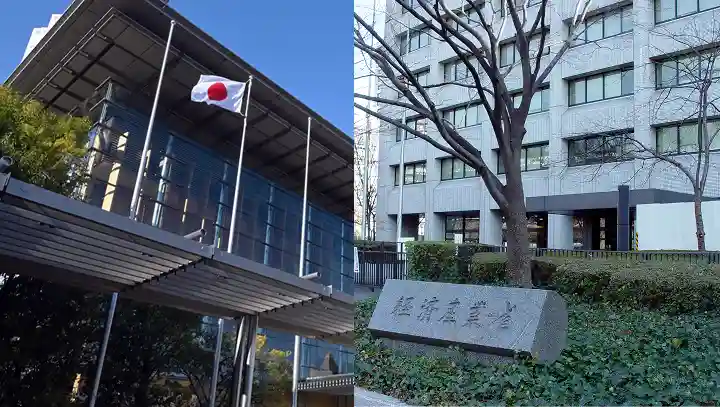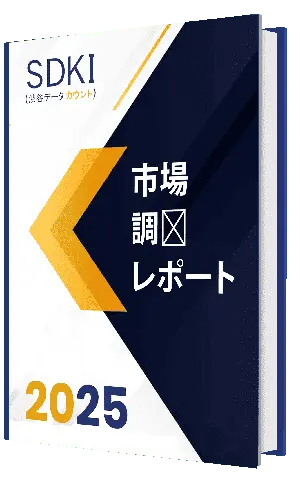回復とリスク:日本の自動車業界は関税の嵐を乗り越えられるか?
SDKI Analytics によって発行されました : Oct 2025

日本経済の成長軌道は緩やかに回復しており、第2四半期(4-6月期)の成長率は予想を上回り、国内市場の見通しが改善していることを示唆しています。しかし、トランプ大統領の関税導入は、特に自動車セクターにおける米国の貿易政策が、大きな逆風となる可能性を示唆しています。
市場アナリストやストラテジストにとって、二つの見方は明確です。日本経済は最近の不安定な状況から回復しつつあるものの、対外政策の導入によってその進展が阻害される恐れがあります。
国内の力強いシグナルは外部の脆弱性によって和らげられています
内閣府の最新の月報では、設備投資と個人消費の両方の評価が引き上げられ、前者は2024年8月以来初めて家計需要の基調的な成長モメンタムを示しています。一方、個人消費は日本のGDPの半分以上を占める顕著な貢献を示しており、この特定の構成要素における持続的な回復が重要であることを示しています。
機械およびデジタル技術への設備投資も増加しており、2024年(3月)以来の重要な修正となっています。一方、日本銀行もリスク資産の保有を削減し、金融政策と経済政策に対するスタンス(タカ派的傾向)を強めました。これは、2人の理事が金利を低水準に維持することに反対した結果です。
しかし、工業統計は脆弱な回復を示しています。日本では、2025年5月の工場生産は前月比わずか0.5%の増加にとどまり、約3.2%という予想を大きく下回りました。逆風の中、一部の製造業は7月の生産量が0.7%減少すると予想していました。予想を下回る工業生産は、貿易摩擦による景況感の低下を浮き彫りにしています。
日本経済は依然として脆弱な状況にあり、これは第1四半期(2025年1-3月期)のGDPが0.7%減少したことに起因しています。これは、国内消費の低迷と輸出の低迷が大きな要因です。この縮小は、米国の関税措置の影響が完全に顕在化する以前から、日本経済が依然として回復に苦戦していたことを明確に示しています。
関税ショック、自動車メーカーに最も打撃
政府は、米国の関税の影響を最も受けている産業は自動車部門であると特定しています。これは、日米合意に基づき、日本からの輸入品に15%の関税が課されることになりました。しかし、これは以前に脅迫されていた物品に対する25%、自動車に対する27.5%の関税率よりも低いものです。それでも、日本の自動車メーカーが慣れ親しんできた以前の関税率2.5%と比べると、大幅な上昇です。
輸出統計は衝撃的な物語を語ります
2025年6月の日本からの米国向け自動車部品輸出は前年比26.7%増加しましたが、5月は24.7%減少しました。輸出数量は前年比4.6%増と小幅な増加にとどまったものの、輸出額は25.3%急落しており、関税の影響を緩和するために大幅な値引きが行われたことが示唆されています。利益率の低下には、円高による価格圧力も一因として挙げられます。
以前のモデル化はリスクの大きさを強調しています
Oxford Economicsによると、日本の機械・自動車セクターは、輸出の大部分を米国が占めているため、トランプ関税の影響を最も受けやすいセクターです。2024年には、米国は日本の輸出の3分の1以上を占めることになります。当初は、米国の関税の25%が日本の自動車生産を約7%縮小させると予想されていました。しかし、BMIによると、自動車関税は日本の実質GDP成長率を0.7-1.1%ポイント押し下げる可能性があります。
日本のOEMは反応しています
Nissan、Honda、Toyotaといった日本の主要自動車メーカーは、米国工場への生産依存度を低減するため、現地生産化戦略を検討しています。さらに、これらの自動車メーカーは、米国以外の市場におけるプレゼンスと事業の拡大、そしてサプライチェーンの刷新と計画策定にも注力しています。
Toyotaは、米国の関税の影響を早期に認識していました。同社は、関税による貿易圧力を考慮し、今年初めに利益見通しを1.4兆円に修正し、純売上高は44%減少すると見込んでいます。
アナリストは戦略再編の必要性を警告
SDKIアナリストは、日本のマクロ経済の傾向は改善していると指摘しています。日本の自動車部品輸出への依存度は、不安定な構造を露呈しています。さらに、SDKIアナリストは、現在の関税シナリオによる貿易圧力を吸収するために、日本の自動車メーカーはイノベーション主導の差別化や市場多様化といったリスク回避戦略を採用する必要があると示唆しています。
SDKIアナリストはさらに、国内需要は回復の兆しを見せているものの、高付加価値機械、自動車、製造業から生じる価格圧力や貿易ショックを相殺するには必ずしも十分ではない可能性があると指摘しています。これを緩和するために、日本はアジア、アフリカ、ラテンアメリカの新興国との二国間貿易枠組みの拡大や、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)など、地域内における貿易関係の強化に重点を置く必要があります。
提言と戦略展望
SDKI Analyticsの専門家はさらに、日本政府が水素燃料電池や電気自動車といった先進的かつ革新的な自動車技術の研究開発と設備投資を支援する財政的インセンティブを提供するよう提言しています。さらに、アナリストは、半導体や部品を中心とした国内サプライチェーン基盤の強化に重点を置くことで、長期的には地政学的な貿易摩擦を緩和できると考えています。
SDKIアナリストは、関係者は効率性を高め、為替変動や関税によるコストショックを相殺するために、スマート製造とデジタルトランスフォーメーションに投資すべきだと提言しています。




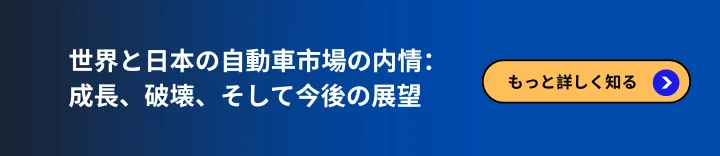
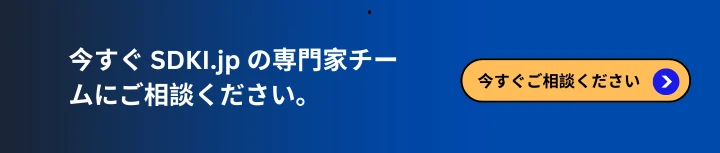
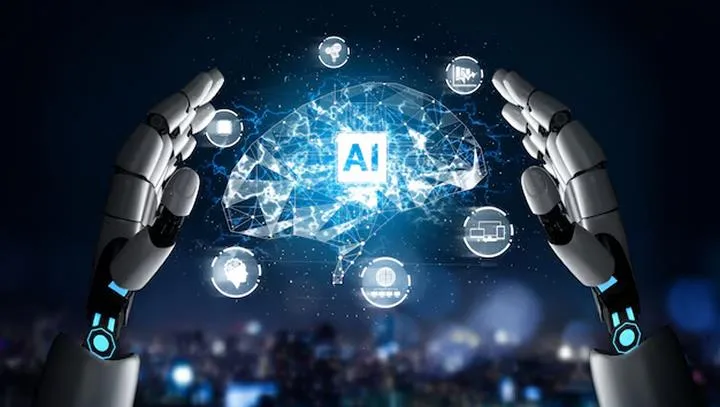
_1765973632.webp)