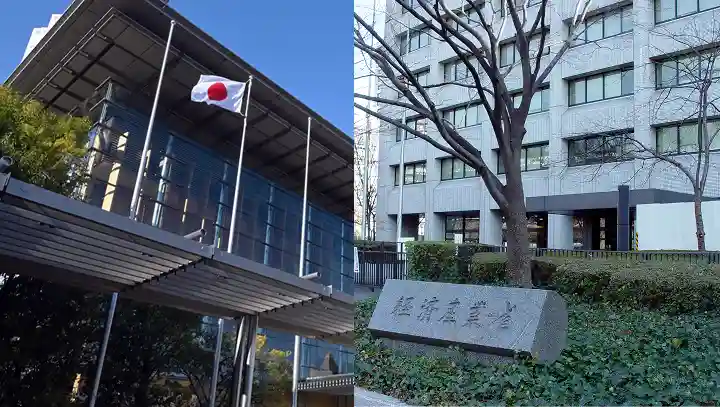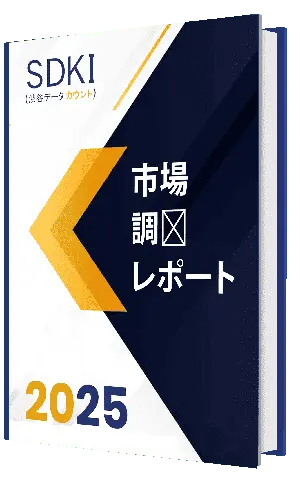日本のおむつリサイクル革命:2025年までに廃棄物を資源に変える
SDKI Analytics によって発行されました : Jun 2025

日本は、国民の90歳以上の出生率が非常に高いという、非常に特殊な問題を抱えている国です。2025年までに国民の35%以上が65歳以上になると推定されています。このシルバーの津波はまた、計り知れない社会的変化をもたらし、その中には大人用失禁用品の需要の急増も含まれています。乳児用おむつを必要とする一定の出生率と相まって、使用済みおむつの数は膨大で、2025年までには年間70億枚という驚異的な数に達すると推定されています。これは現在、すべての都市固形廃棄物の約6.5%に相当し、この割合で進むと、埋立地が膨張します。しかし、日本はそれを黙って受け入れるのではなく、おむつリサイクルの世界的なトレンドをリードし、廃棄物問題全体を新しい通貨に変えています。
課題の規模(2025年データスナップショット):
日本人は毎年約70億枚のおむつを廃棄しており、国民一人当たりの排出量は約19百万枚で、これは重量で家庭ごみ全体の約6.5%に相当します。現在の廃棄手順では、時間と貴重なスペースを浪費するため埋立地に大きな負担がかかり、自治体が毎年埋立地に支払う廃棄料金は90百万米ドル以上に上ります。金銭的コストと環境的コストに加え、おむつは分解時に強力な温室効果ガスであるメタンを排出し、地下水を汚染する恐れがあります。人口動態の変化の原因の1つは、日本の人口の高齢化(65歳以上の人口が40百万人以上)です。高齢化により、乳児よりも大人用おむつを使用する人が増え、これが廃棄物処理を複雑にしているのです。
革命の誕生:必要性と革新の出会い
この差し迫った危機を受け、日本の企業、自治体、研究機関は長期的な解決策を模索し始めました。ビジョンはシンプルでしました。埋め立て地に捨てられるおむつを取り除き、貴重な資源を再利用することです。これは非常に困難な課題でしました。おむつは複雑な複合材料であり、問題は山積みでしました。おむつは、高吸水性ポリマー(SAP)、プラスチック(PE/PP)、パルプ(フラッフパルプ)、そして有機廃棄物が高度に複合された素材だからです。
以前の研究では、堆肥化が最初の段階でしたが、汚染への懸念と合成素材の分解の遅さから、効果は限定的でしました。真に注目を集めたのは、おむつの中身を分解・洗浄できる優れた機械的・化学的リサイクルシステムの発明でしました。
変化を推進するテクノロジー(2025年の状況):
日本のおむつリサイクルのエコシステムは、2025年までに開発され、高度に先進的ですぐに使用できる施設を基盤としています:
1. 超臨界水リサイクル(Unicharm と Shimadzu):
これは画期的な技術であり、主力技術です。
- プロセス:湿らせた細断されたおむつを、高圧(374℃以上、218気圧)の加熱水が流れている反応槽に入れます。これにより、いわゆる超臨界水が生成され、水は高い浸透性を持つ効果的な溶媒として機能します。
- 分離の魔法:超臨界水は、分解可能な有機物(糞便、尿残留物、パルプ繊維)を滅菌された液体肥料成分またはバイオガス原料に分解する非常に効率的な方法です。重要なのは、同時にSAPを無効化し、プラスチック部品(バックシート、タブ)を無傷のまま分解することです。
- 2025年の生産量:1つの工場(Unicharmの大規模工場は2023年に稼働済み)で、毎日75トンの使用済みおむつを生産できます。出力には以下が含まれます:
- 高純度リサイクルプラスチックペレット(PP/PE):食品用以外のプラスチック製品(例:公園のベンチ、パレット、建築資材)に使用されます。回収率は投入プラスチックの90%以上です。
- 不活性SAP/フラッフパルプスラリー:通常は土壌改良剤として消化されますが、エネルギー源として利用される場合もあります。
- 滅菌済み液体有機分画:追加加工を施すことで農業用途にも適しています。
- 利点: 高い効率、プロセスの一部である無菌性、高純度の製品、混合廃棄物ストリームを有利に処理します。2025年までにスケーラビリティが実証されます。
2. 高度な機械リサイクルとSAP回収:
- プロセス: 多段階の細断、高度な分離 (スクリーン、空気分級機、光学選別機を使用)、洗浄、乾燥を使用します。清浄なプラスチックフレークの回収方法、そして最近では精製されたSAPの再活性化に重点が置かれています。
- 2025年の焦点:多くの企業がSAPの再活性化を習得しています。精製後、SAPの吸収力を約90%回復させることが可能であり、結晶は新しい衛生用品(厳格な法律に基づき)に再配合されたり、農業用貯水製品に利用されています。
- 出力:高価値のリサイクルSAP(rSAP)と清浄なプラスチックフレークです(超臨界出力と同様の用途)。低品質の用途やエネルギーは、パルプ繊維の形で回収されます。
- 利点:予備段階でのエネルギー所要量が少なく、rSAP製品が重要です。良好な動作には、極めて清浄な原料ストリームが必要です。
3. 前処理を伴う統合廃棄物エネルギー(WtE):
- プロセス:おむつをスライスし、天日干しします。プラスチック部分はさらに選別され、廃棄物固形燃料(RDF)または固形回収燃料(SRF)として、専用の廃棄物焼却施設で効率的に燃焼されます。バイオガスは、有機物の消化によって代替可能です。
- 2025年の役割:少なくとも、材料リサイクルが可能なほど十分に汚染されていない水路にまだ回収されていないおむつへの重要なルートであり続けます。効果的な埋立処分場転換オプションとエネルギー生産を提供します。より効率的であるため、排出量を最小限に抑えることができます。
エコシステム:収集、政策、そして市民参加(2025年の展望)
単一の技術ではだめです。日本はそれを支える巨大なエコシステムを構築してきました:
- 自治体による回収制度:2025年までに、1,250以上の自治体(約75%)が使用済みおむつの回収制度を導入しています。これらの制度には、一般廃棄物と一緒に回収される専用回収袋、老人ホーム、保育施設、スーパーマーケットへの持ち込みなどがあります。対象となる自治体の分別率は70%前後です。
- 政策要因:循環型経済・循環型社会形成に向けた政府の取り組みによって枠組みが整備されました。埋立処分費用の規制はコスト増加につながりました。2024年改正リサイクル法は、おむつを含むより処理困難な廃棄物の高度なリサイクルを推進するための、自治体へのより明確な義務を盛り込むことで、この枠組みを直接的に強化しています。
- 業界の取り組み:Unicharm、Kao、Daio Paperなどの大手メーカーは、リサイクル技術の開発に取り組んでいるだけでなく、回収インフラや消費者教育にも多額の投資を行っています。Unicharmは、自社のリサイクルシステムを導入する自治体に補助金を提供することができます。
- 国民の受容:環境責任(もったいない - 無駄をなくす)に関する数十年にわたる全国的な意識啓発キャンペーンと、高齢化社会における日本社会のニーズとの直接的な関連性により、国民の参加率は非常に高くなっています。調理方法(固形物を取り除く、時々部品を分ける)に関する明確な指示が広く普及しています。
2025年の具体的な影響:
革命は測定可能な変化をもたらしています:
- 埋立処分量の削減:日本では、リサイクルと廃棄物処理を通じて、年間約1.2百万トンの使用済みおむつが埋立処分されています。これは、ほんの数年前までははるかに少なかった量です。
- 資源回収:日本のリサイクル工場では、既に使用済みおむつから再生されたプラスチックペレットが155,000トン以上、さらに約55,000トンの再活性高吸水性ポリマー(rSAP)が生産されており、これらは新たな市場への進出も進んでいます。また、土壌改良材や堆肥、バイオガスも大量に生産されており、これらすべてが循環型経済の一環をなしており、従来の廃棄物処理プロセスへの依存を低減しています。
- 経済活動:おむつリサイクル産業などの活動は、回収、処理、研究開発、そしてリサイクル製品を使用した再製造において、数千もの雇用機会を支えています。回収された材料の販売は、回収・処理費用の一部を補助しています。
- カーボンフットプリント削減:ライフサイクルアセスメントによると、高度なリサイクル(特に超臨界水と効率的な材料回収)は、埋め立てに比べて温室効果ガス排出量を45%削減します。効率的な前処理も、廃棄物発電(WtE)が使用されている埋め立てに比べて純利益をもたらします。
- 世界的なリーダーシップ:このニッチ分野における世界のリーダーは日本です。日本の技術は、特に高齢化の影響を受ける韓国、ヨーロッパ、中国といった国々や、一般廃棄物問題に悩む国々から、国際的に強い注目を集めています。
課題と今後の展望:
彼らの目覚ましい成功にもかかわらず、挫折は依然として存在しています:
- 収集規模と純度:リサイクル効率と生産物の品質を最大化するには、自治体の105%に収集を拡大し、分別の純度を高めること(おむつ以外の廃棄物の削減)が不可欠です。地方部における輸送は課題です。
- コスト競争力:高度なリサイクルプロセスは埋め立てや簡易焼却に比べてコスト上昇を招くものの、リサイクルは改善しました。研究開発に加え、規模の拡大、相互補助金、そして政策(2025年の法制化で加速する拡大生産者責任制度など)の推進が求められます。
- 最終市場の開発:すべてのリサイクル製品(特にrSAPと回収パルプ)において、安全で高付加価値な市場を確立するには、長期的な経済性が必要です。rSAPの繊細な用途への承認はまだ進行中です。
- 衛生と認識:排泄物のリサイクルに伴う不快感の問題については、厳格なプロセスとそれに続く滅菌について、継続的な啓発とオープンな議論が必要です。
結論:実践的イノベーションのモデル
日本におけるおむつリサイクル革命は、単なる廃棄物管理の成功物語ではありません。創造性、技術力、そして科学的連携によって、深刻な社会課題に取り組む日本の能力を実証するものです。人口高齢化の避けられない影響を懸念する日本は、廃棄物そのものに目を向けるのではなく、むしろ機会として捉えました。
この革命は2025年に本格化します。最先端の超臨界水処理プラントであれ、精巧な機械式SAP回収装置であれ、日本は、処理が最も困難な廃棄物でさえもリサイクル可能であることを証明しています。地中に埋められるはずだった何百万トンものおむつが、今やプラスチックペレット、再生超吸収剤、土壌改良剤、そしてエネルギーという形で第二の人生を送っています。経済的および環境的コストは、物理的コストであると同時に、増大しています。
旅の終わりではありません。今後も収集規模の拡大、コストの最適化、そして最適な最終市場の開拓を続けなければなりません。しかし、日本は既にこのコンセプトを実証し、インフラを整備することに成功しています。おむつリユース運動は、世界に印象的なロードマップを提供し、意志の力と創造性があれば、たとえごく個人的な廃棄物であっても、完全な循環型経済への道筋を実現できることを教えています。世界的な高齢化が進む中、日本で培われた知識と技術は、地域のニーズに応えるだけでなく、持続可能なソリューションの世界的な基準となることで、ますます重要性を増していく可能性があります。
関連トピック:




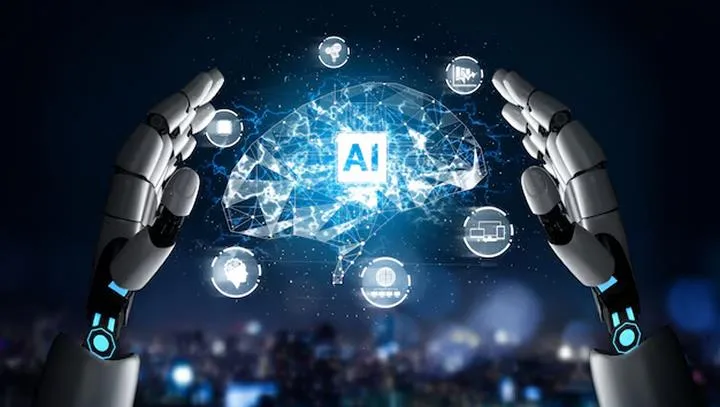
_1765973632.webp)